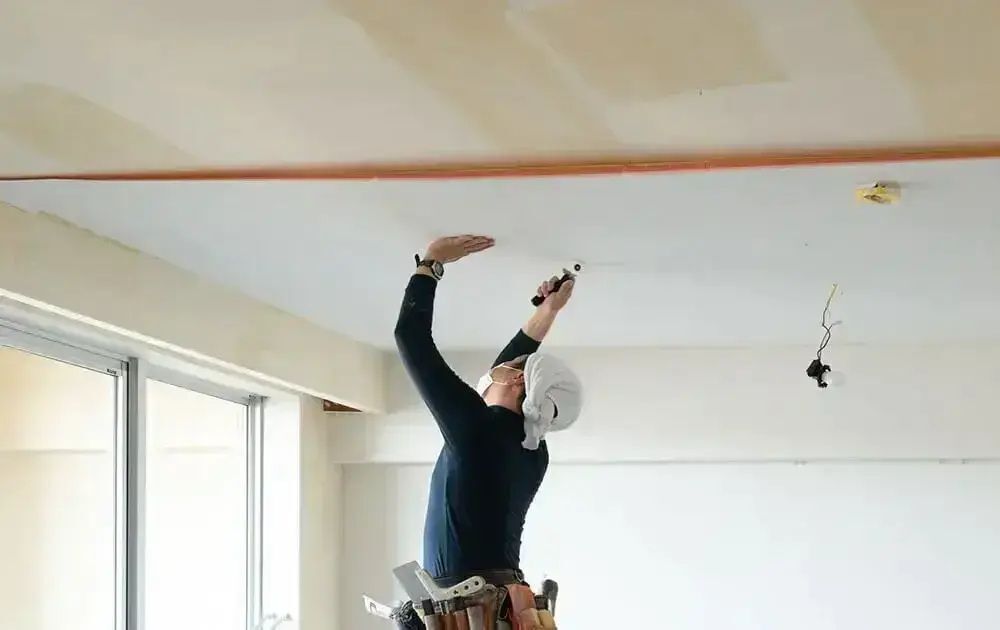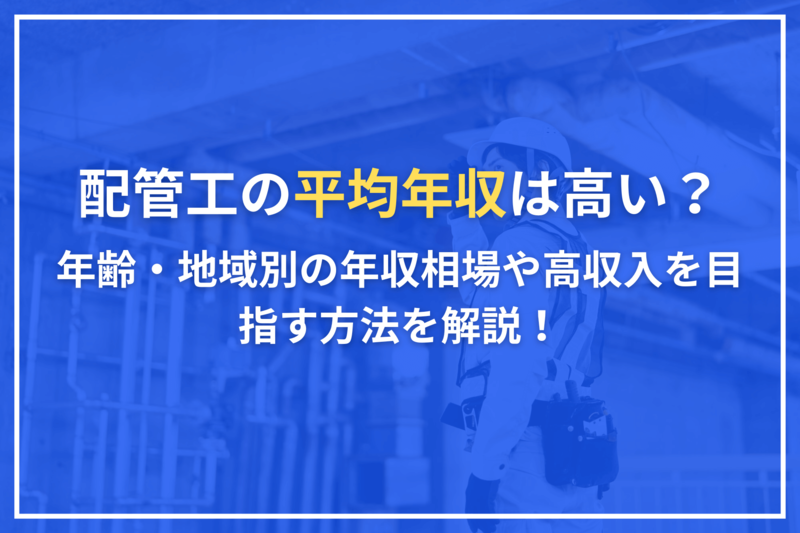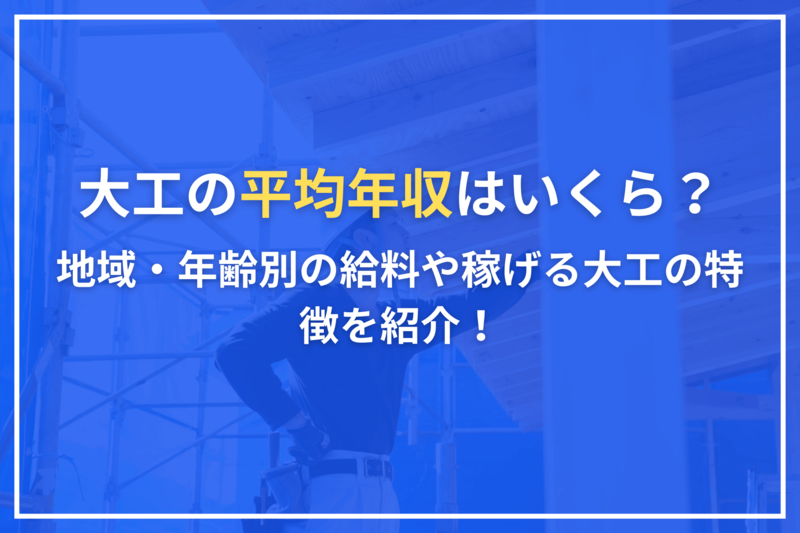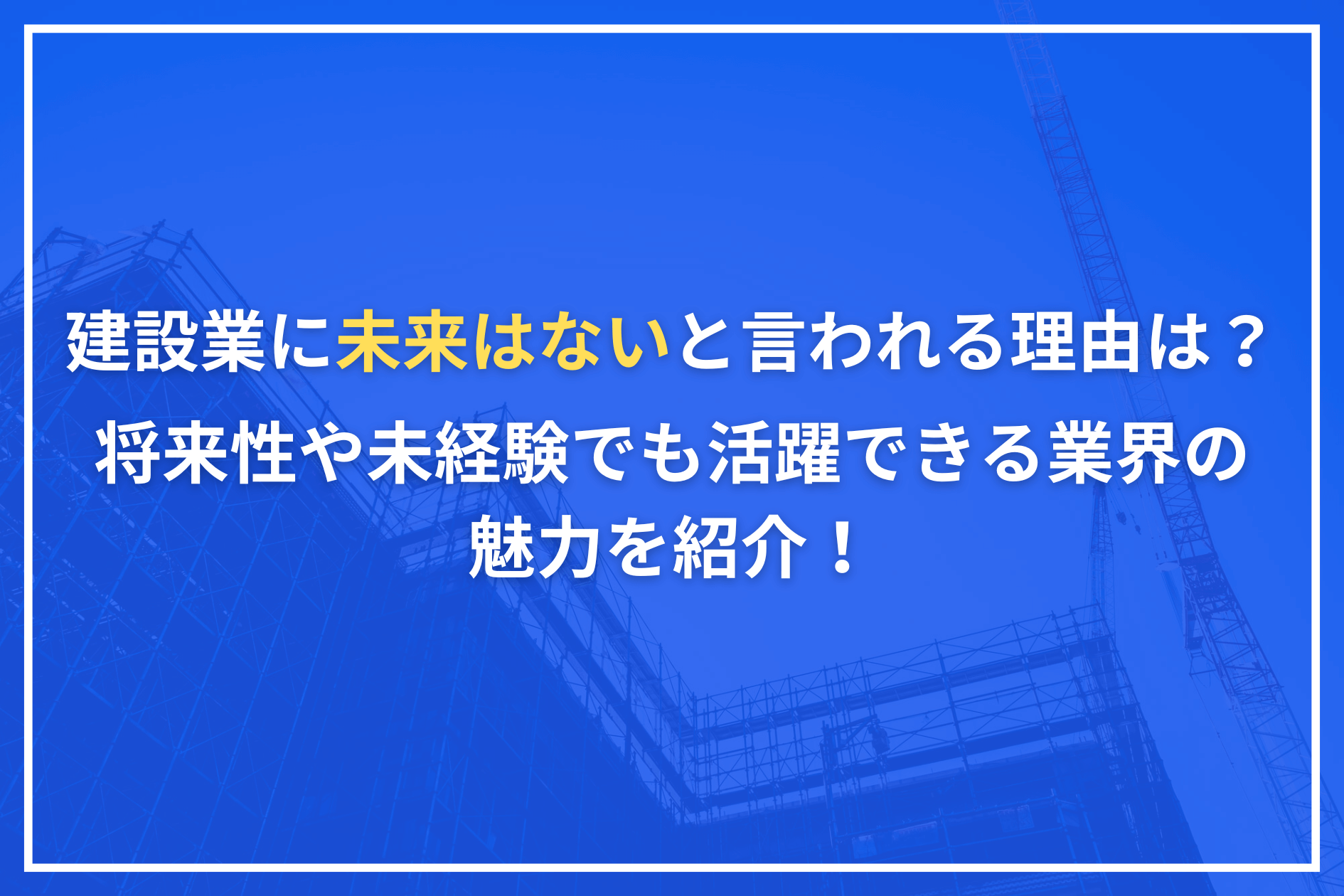
「建設業界はもう時代遅れだ」「きつくて未来がない」。
そんなネガティブなイメージが、いつの間にか定着してはいないでしょうか。確かに、会社によっては長時間労働や人手不足といった厳しい課題があるのは事実です。
しかし、そのイメージだけで判断してしまうのは、あまりにもったいないかもしれません。 実は今、建設業界は国を挙げた働き方改革と技術革新によって、大きな変革期の真っ只中にあります。他業種をしのぐほどの高い給与水準を実現し、未経験者がゼロからプロフェッショナルを目指せる「チャンスに満ちた業界」へと生まれ変わりつつあるのです。
この記事では、「未来がない」と言われる理由を解き明かしながら、その先にある建設業界の確かな将来性と、今だからこそ注目すべき魅力を紹介します。
建設業に未来はないと言われる理由

「建設業の2024年問題」や「2025年問題」など、業界の先行きを不安視するニュースが後を絶ちません。こうした懸念には、次のような理由が存在します。
労働環境の改善が進まない
建設業界では、厳しい納期を守るため、長時間労働や休日出勤が長らく常態化してきました。多くの現場で労働時間の管理が徹底されておらず、労働環境の改善は進んでいるとは言い難い傾向があります。
賃金がなかなか上がらない
建設業界は、元請けを頂点に、下請け、孫請けへと続くピラミッド型の重層構造になっています。この多重下請構造により、末端の事業者や作業員まで費用が適切に配分されにくく、現場で働く人々の賃金が上がりにくいという問題が指摘されています。
深刻化する人手不足と技術継承の課題
少子高齢化の波は建設業界にも押し寄せ、若手の担い手が減少する一方で、熟練工の高齢化が深刻です。特に、経験豊富な団塊世代が大量に退職する時期を迎え、長年培われてきた貴重な技術やノウハウの継承が危ぶまれています。この人手不足は、若手への負担増やプロジェクトの品質低下・遅延にも繋がりかねません。
AIやICTの導入が遅れている
他業界と比較して、建設業界はAIやICT(情報通信技術)の活用が遅れていると言われています。現場では依然としてFAXや紙の書類が多用されるなど、デジタル化への移行が進んでいません。これには、デジタルツールに不慣れな高齢の技術者が多いことも一因とされ、生産性の向上や労働環境改善の足かせとなっています。
多重下請構造の問題
どうしても下請けになるほど皺寄せがきつくなり、スケジュールやコスト面で無理を強いられる……ということに警鐘が鳴らされています。また1次請け(元請け)から2次請け(下請け)に圧力がかかるなど、透明性についても問題視されています。
建設業の将来性は明るい?求職者にとって「狙い目」な理由とは

しかし、「未来がない」という見方は、もはや過去のものとなりつつあります。数々の課題に対し、国と業界が一体となって改善に取り組んでおり、建設業界は今、大きな変革の時を迎えています。むしろ求職者にとっては、大きなチャンスを秘めた「狙い目の業界」と言えるでしょう。
具体的に今、建設業界はどのように変わりつつあるのか見ていきましょう。
拡大する市場規模
日本のインフラは、高度経済成長期に整備されたものが多く、老朽化が深刻な社会的課題となっています。これらの維持・修繕工事は、人々の安全な暮らしを守るために決してなくならない仕事です。さらに、都市部では大規模な再開発プロジェクトが次々と進行しており、建設市場は今後も安定した需要が見込まれています。
賃金は増加傾向
実は、建設業界の平均年収は他産業と比較しても高く、常に上位にランクインしています(※1)。公共事業で働く労働者の賃金の基準となる「公共工事設計労務単価」は10年以上も連続で上昇(※2)。国土交通省による2024年度の建設投資は、前年度比2.7%増の73兆200億円と言われています。(※3)
》建設業の平均年収って実際どう?国の最新統計で業界別・職種別に徹底比較!
新技術の導入
「新しい技術」と聞くと、「難しそう…」「覚えるのが大変そう…」と感じますが、建設業界で導入が進む新技術は、あなたの仕事を奪うものではなく、あなたの身体を楽にし、安全を守るための力強い味方です。
ドローン・遠隔カメラ
これまで職人さんが直接行っていた高所や足場の悪い場所での確認・測量作業は、ドローンが代わりに行います。あなたは安全な場所からモニターを見るだけ。危険な作業やそれに伴うヒヤリハットが劇的に減ります。
ICT建機
夏の炎天下でのきつい掘削作業や、ミリ単位の精度が求められる整地作業。これらをGPSやセンサーを搭載したICT建機が、まるでゲームのように正確に、そして自動でアシストしてくれます。体力的な負担が減ることで、身体へのダメージを気にせず、長く元気に働き続けられます。
BIM/CIM
分厚い紙の図面とにらめっこする必要はもうありません。スマホやタブレットに映し出された3Dモデルを指でくるくる回せば、完成形や複雑な部分の構造が一目瞭然。新人でもベテランでも同じ完成イメージを共有できるので、「指示が分かりにくい」「間違えてやり直し」といったストレスがなくなります。
AIでは代替が効かない仕事
一新技術の導入と聞くと、AIに人の仕事が取って代わられるのでは……と将来への不安要素となるかもしれません。しかし、建設業界の仕事はAIでは代替しにくく、やはり最終的には「人の手」と「人の目」が不可欠です。最新技術はあくまで「人を助ける」ものであり、現場の主役はこれからも人なのです。
働き方改革の適用
024年4月、建設業界にも「働き方改革関連法」が適用され、時間外労働の上限規制が始まりました。これにより、長時間労働の是正が本格化。週休二日制の導入や有給休暇の取得も推進されており、「きつい、汚い、危険」といった3Kのイメージは過去のものとなりつつあります。
建設会社の経営者も代替わりしており、かつて3Kあるいはブラックと言われた時代に自分が味わった辛さを、若い世代に感じさせたくないと改善に取り組む経営者も増えています。
<参考文献>
(※2)国土交通省|令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について~今回の引き上げにより、13年連続の上昇~
(※3)国土交通省|令和6年度(2024年度)建設投資見通し
未経験でも活躍できるチャンスが広がっている

このように、建設業界に「未来はない」どころか、働きやすく、チャンスにあふれる業界へと生まれ変わっています。特に、未経験者にとっては挑戦しやすい環境が整いつつあります。
未経験でも活躍できる理由とは?
「専門的な仕事だから、未経験では無理だろう…」そんな心配は無用です。現在の建設業界には、未経験者を着実に成長させる育てるための、万全の環境が整っています。
多くの企業では、入社後の研修が充実しており、道具の名前や使い方、安全ルールといった基礎の基礎から丁寧に学ぶことができます。その後は、先輩がマンツーマンに近い形で指導するOJT(現場研修)に移行。チームの一員として簡単な作業から始め、段階的に仕事の範囲を広げていくため、一人で放り出されるようなことはありません。
さらに、「資格取得支援制度」を設けている企業も多くあります。働きながら国家資格に挑戦でき、取得すれば資格手当として給与もアップ。あなたの「頑張り」が、目に見えるスキルと収入に直結するのです。必要なのは今の経験や知識ではなく、「学びたい」という意欲。それさえあれば、誰もがプロを目指せる道が用意されています。
未経験OKの会社は多い
たしかに即戦力となるのは経験者ですが、これからの業界を担う若手を育てたいと、未経験者を積極的に採用する建設会社も増えています。
そのため、多くの会社が学歴や経験を問わず、「やる気」を重視した採用を行っています。特にニーズの高い「現場作業員」は、未経験からスタートしても、現場でスキルを磨き、資格を取得することで、着実なキャリアアップと大幅な給与アップが期待できる魅力的な職種です。
》現場仕事の種類って何がある?現場のリアルなやりがいや未経験からの始め方を紹介
まとめ

労働環境の遅れや多重下請構造といった課題から「未来はない」と言われた建設業界ですが、その姿は今、大きく変わろうとしています。
インフラの維持・更新という社会に不可欠な役割を担い、市場は安定。給与水準も他業界より高く、将来性は盤石です。働き方改革やデジタル技術の導入によって、かつての過酷なイメージは払拭され、若者や未経験者が働きやすい環境へと進化を遂げています。
経験や学歴は関係ありません。未来の日本を創り、社会を支える。そんなやりがいのある仕事に、未経験から挑戦できるチャンスが、建設業界には広がっています。
建設業界への挑戦、まずは『キャリコンジョブ』で探してみよう
この記事を読んで、建設業界の未来に可能性を感じた方も多いのではないでしょうか。その思いを、具体的な行動に移してみませんか?
建設業界に特化した求人サイト「キャリコンジョブ」では、未経験からプロを目指せる研修制度が整った会社や、あなたの新しい挑戦を温かく迎えてくれる企業の求人を多数掲載しています。
まずは「どんな仕事があるんだろう?」と、あなたの未来の選択肢を覗いてみることから始めてみませんか。
建設業界への第一歩を踏み出すなら、ぜひ「キャリコンジョブ」をチェックしてみてください。


.png)

.png)