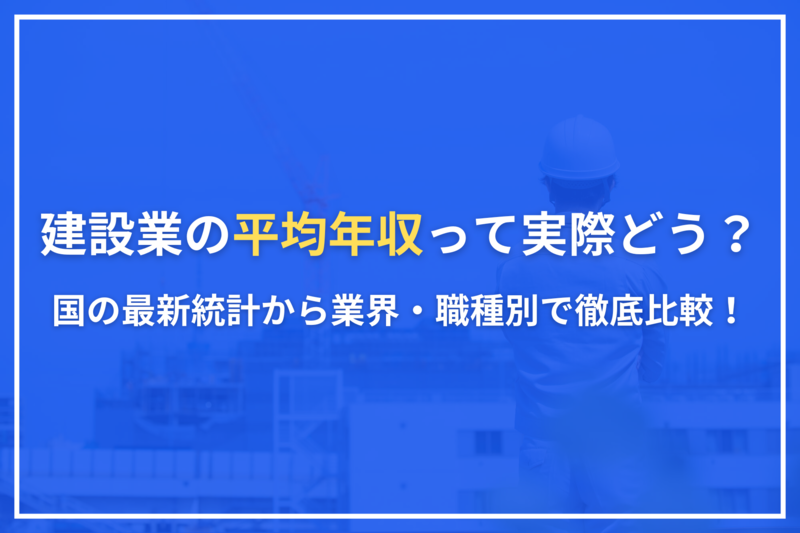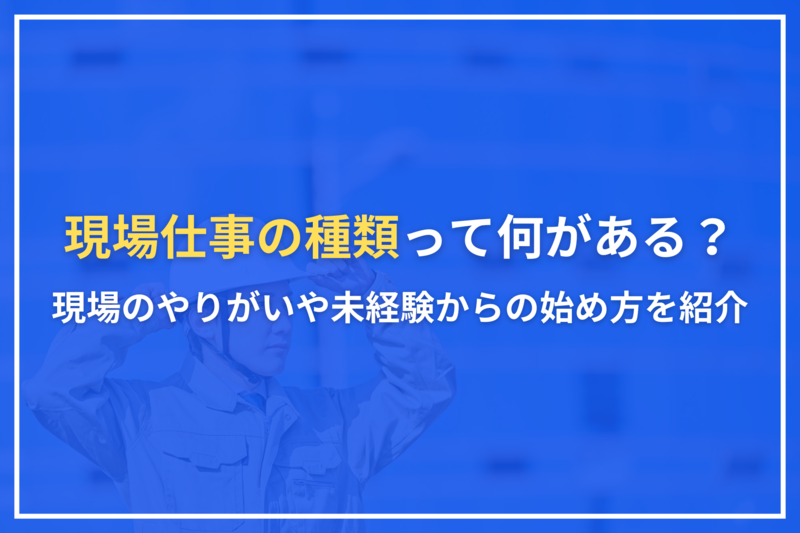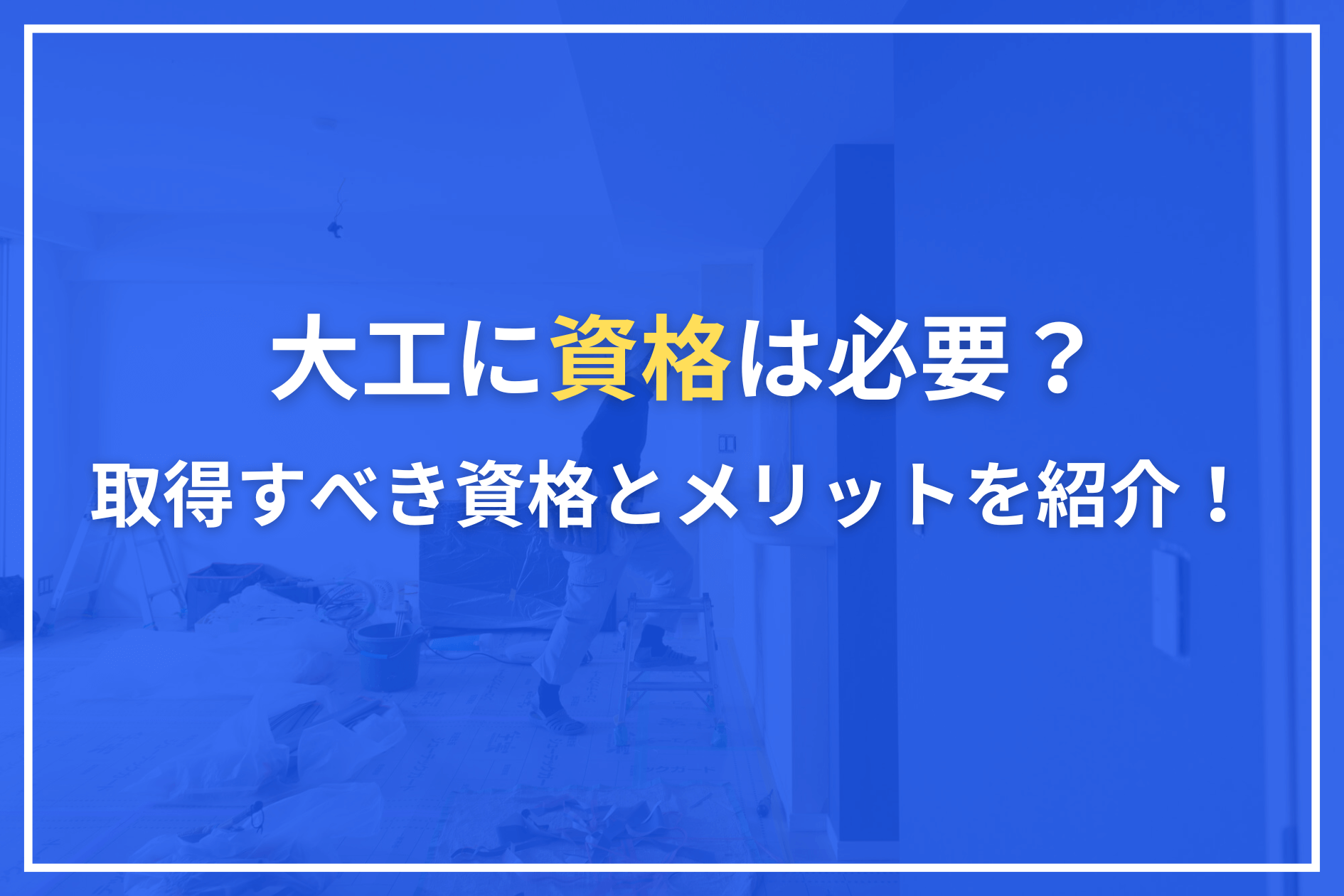
「手に職をつけたい」「建築の世界で活躍したい」――そんな思いから大工という職業に興味を持つ方は多いのではないでしょうか。住宅や商業施設の建築、リフォームや増改築まで、私たちの暮らしを支える大工の仕事は、今も変わらず社会に欠かせない重要な役割を担っています。
しかし、いざ大工を目指そうと思っても、「資格は必要?」「どうやって始めるの?」「どんな資格が役に立つの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。特に近年は、建設業界全体で技術者不足が進んでおり、若手人材の需要が高まる一方、専門性や資格の有無が重視される傾向にあります。
この記事では、大工になるために必要な資格の有無や、実際に役立つ資格の種類・取得メリットなどを、わかりやすく解説していきます。これから大工を目指す方や、キャリアアップを目指す現役の方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
大工に資格は必要?

結論から言うと、大工になるために特定の資格が必須というわけではありません。実際、多くの現場では見習いから経験を積んで一人前になるスタイルが残っています。特に住宅建築の現場では、資格を持たない大工も多く活躍しています。しかし、プロの大工として活躍するには、建築に関する専門的な知識や高度な技術の習得が不可欠です。
資格がなくても大工の道へ進むことは可能ですが、資格があれば活躍の場が広がり、就職や転職で有利になることが多いでしょう。キャリアアップや将来的な独立開業を目指すなら、資格取得は大きな後押しとなります。
また、現場のリーダーなど特定の役職に就いたり、公共工事を受注したりする際には、資格が必須条件となるケースもあります。
大工の世界は学歴や年齢が問われにくい傾向があり、中学卒業後に親方に弟子入りする人もいれば、高校・専門学校・大学などで建築を学んだ後、工務店に就職して技術を磨く人もいます。ただし、一部の上位資格を取得するには、高校や高等専門学校、大学で土木・建築関連学科を卒業していることが条件となる場合があります。将来的なキャリアアップを見据えるなら、進学して専門知識を深めることも有効な選択肢です。
大工の仕事内容と資格が役立つシーン

大工の主な仕事は、木造建築物の新築、増築、リフォーム工事などです。設計図を正確に読み取り、木材を加工・組み立てて建物を形にしていく、まさに"ものづくり"のプロフェッショナルと言えるでしょう。
ひとくちに大工といっても、その専門分野はさまざまです。一般的にイメージされるのは、戸建て住宅などを手掛ける「家屋大工」でしょう。そのほか、障子やふすまなどを作る「建具大工」、神社仏閣の建築・修繕を専門とする「宮大工」など、担当する仕事内容によって呼び名や求められる技術も異なります。
資格は、あなたのスキルや知識を客観的に証明するものです。そのため、就職や転職活動において大きなアピールポイントとなります。資格取得は自身の市場価値を高めることにも直結し、結果として、より幅広い業務や責任ある仕事を任されるチャンスが増え、キャリアアップにつながっていくでしょう。
【目的別】大工が取得すべきおすすめ資格

大工に関連する資格は多岐にわたりますが、ここでは目的別に必要な資格を紹介します。まずは基礎となる資格から、そしてキャリアの幅を広げる資格へと進んでいきましょう。
【まず取得したい!基本となる資格】
大工の仕事をする際にまず取得しておきたい資格は、「建築大工技能士(3級・2級・1級)」と「木造建築物の組立て等作業主任者」です。それぞれの資格について解説します。
建築大工技能士(3級・2級・1級)
木造建築における大工工事の技能レベルを証明する国家資格です。レベルに応じて3級(初級)、2級(中級)、1級(上級)があり、1級の取得には実務経験が必要です。学歴等によっては実務経験なしで受験可能な3級、比較的短い実務経験や学歴等で受験できる2級から挑戦するのが一般的です。1級を取得すれば、建設業法上の専任技術者や主任技術者になることができ、活躍の場がさらに広がります。
木造建築物の組立て等作業主任者
労働安全衛生法に基づく作業主任者資格(国家資格)の一つです。軒の高さが5m以上の木造建築物の骨組み組立や、屋根・外壁下地の取り付け作業など、危険を伴う作業現場において、安全管理の責任者として配置が義務付けられています。現場の安全を守る上で重要な資格です。
【キャリアアップ、仕事の幅を広げる資格】
さらなるキャリアアップや仕事の幅を広げたい場合に役立つ資格の中から、特に活躍の場が広がる「二級建築士/木造建築士」と「2級建築施工管理技士」を紹介します。
二級建築士/木造建築士
建築物の設計や工事監理を行うための国家資格です。 二級建築士を取得すると、一定規模までの建築物(木造・非木造)の設計・工事監理が可能になります。専任技術者や主任技術者としても認められるため、就職・転職で有利になるだけでなく、給与アップも期待できるでしょう。
木造建築士は、その名の通り木造建築に特化した国家資格で、木造建築物の設計・工事監理を行います。木造住宅はもちろん、歴史的建造物の修繕などにも携わることができ、木造建築のエキスパートとして活躍できます。二級建築士と同様、キャリアアップや給与アップにつながる資格です。
2級建築施工管理技士
建築工事全体のマネジメントを行うための国家資格です。具体的には、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などを担当します。この資格を取得すると、一般建設業の営業所に置かれる専任技術者や、工事現場の主任技術者として活躍できます。現場を管理する重要な役割を担うため、責任は大きくなりますが、その分待遇面の向上も期待できます。
資格取得で得られる4つのメリット

大工として働く上で、資格を取得することには多くのメリットがあります。ここでは主な4つのメリットを見ていきましょう。
年収アップを目指せる
資格を取得し、対応できる業務が増えたり、より責任あるポジションを任されたりすることで、給与アップにつながる可能性が高まります。また、多くの企業では、特定の資格を持つ従業員に対して資格手当を支給しています。これは、専門スキルや知識を評価する制度であり、取得すればさらなる収入増が期待できます。
》大工の平均年収はいくら?地域・年齢別の給料や稼げる大工の特徴を紹介!
対応できる業務範囲が広がる
大工の仕事には資格なしでできる作業もありますが、特定の作業では資格が必須です。資格があれば、これらの業務も担当できるようになり、仕事の幅が大きく広がります。例えば、二級建築士や木造建築士の資格があれば、設計・工事監理といった、より上流の工程にも関わることが可能です。一人親方(個人事業主)として独立する場合も、資格は信頼の証となり、仕事の受注機会を増やす上で有利に働くでしょう。
転職に有利になる
資格は、あなたのスキルレベルを客観的に証明するものです。転職活動においては、企業が求める資格を持っていれば、強力なアピールポイントとなり、選考を有利に進めやすくなります。資格取得を通じて自身の市場価値を高めることは、より良い条件での転職を実現するための重要なステップです。
社会的信用度がアップする
資格は、専門知識と技術力の証明であり、大工としての社会的信頼性を高めます。資格を持っていることは、他の大工との差別化にもつながります。お客様は安心して仕事を依頼しやすくなり、結果として安定した受注につながることが期待できるでしょう。
まとめ

大工という仕事は、時代が変わっても人々の暮らしに欠かせない重要な職業です。
大工として働く上で資格は必須ではありませんが、取得することで活躍の場が広がり、キャリアアップや収入アップを実現しやすくなります。将来を見据えて大工としてのキャリアを築いていくなら、計画的な資格取得をおすすめします。
大工関連の資格には、比較的挑戦しやすいものから高度な専門性が求められるものまで様々です。まずは、基礎固めとして建築大工技能士や木造建築物の組立て等作業主任者の取得を目指し、ステップアップとして二級建築士や2級建築施工管理技士など、目標に応じた資格に挑戦していくと良いでしょう。
これから大工を目指す方も、すでに現場で働いている方も、自身の目的やキャリアに合わせて資格取得を前向きに検討してみてください。「技術×資格」があれば、あなたのキャリアは確実にひらけていくでしょう。
大工の求人を探すなら「キャリコンジョブ」
大工としてさらなる高みを目指したい、あるいは未経験から手に職をつけたいと考えているなら、建設業界特化の「キャリコンジョブ」がおすすめです。
全国各地の大工の求人が掲載されており、未経験者歓迎の求人から、経験やスキルを活かせる専門職、より責任あるポジションの募集まで、あなたの現在の状況やこれからの目標に合った仕事を見つける手助けになるかもしれません。
大工としての新たな一歩を踏み出すなら、キャリコンジョブで可能性を広げてみませんか。