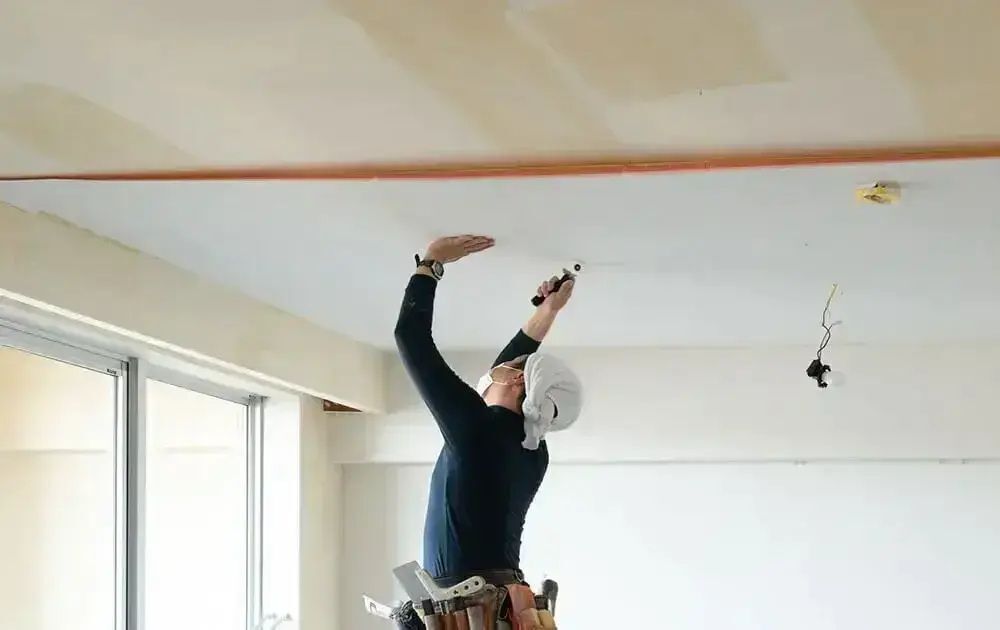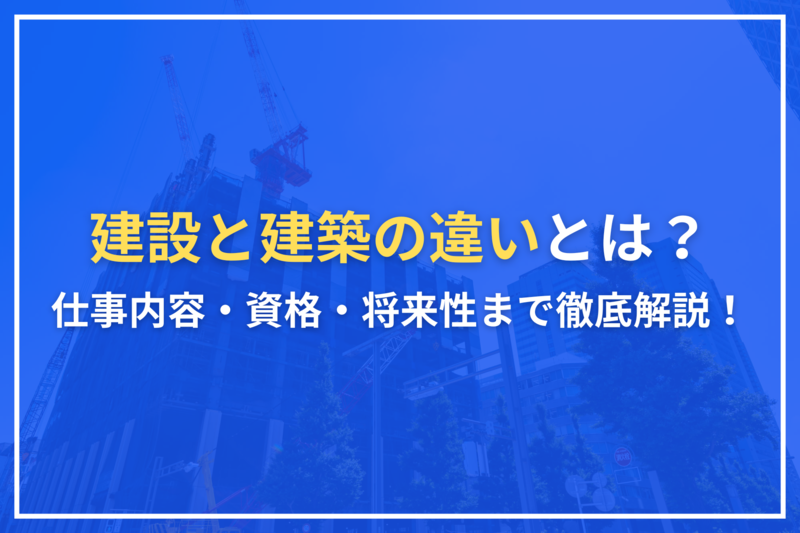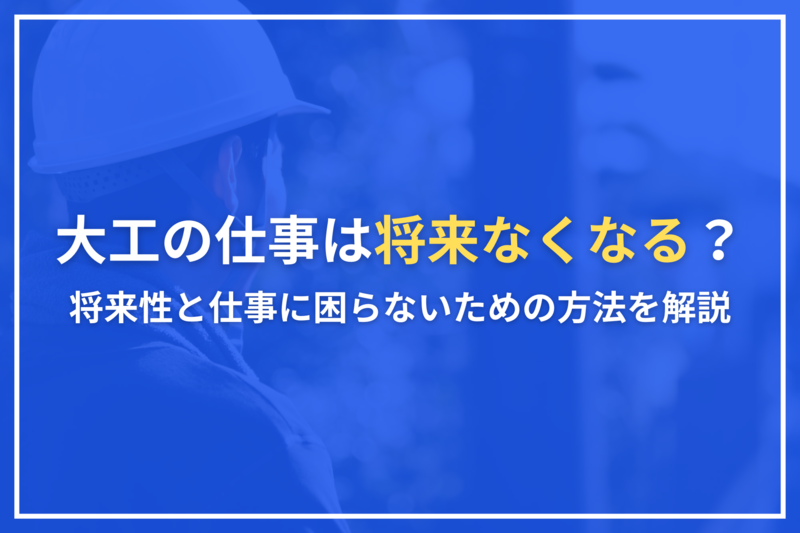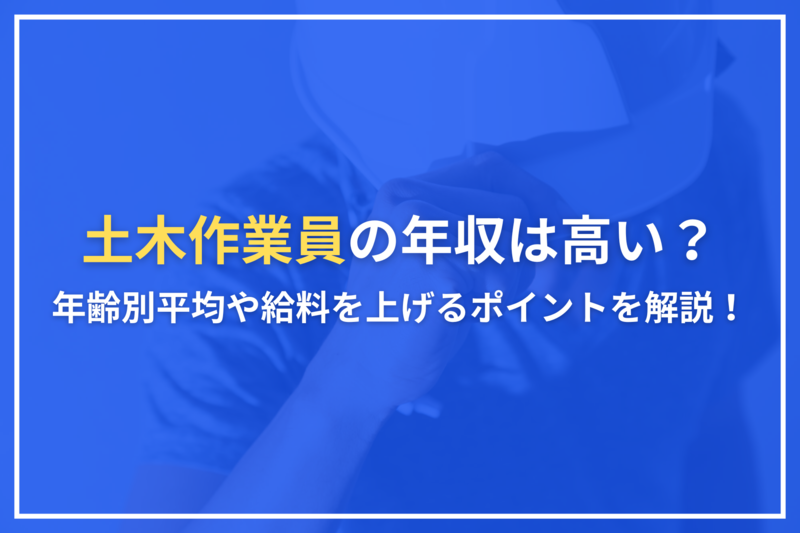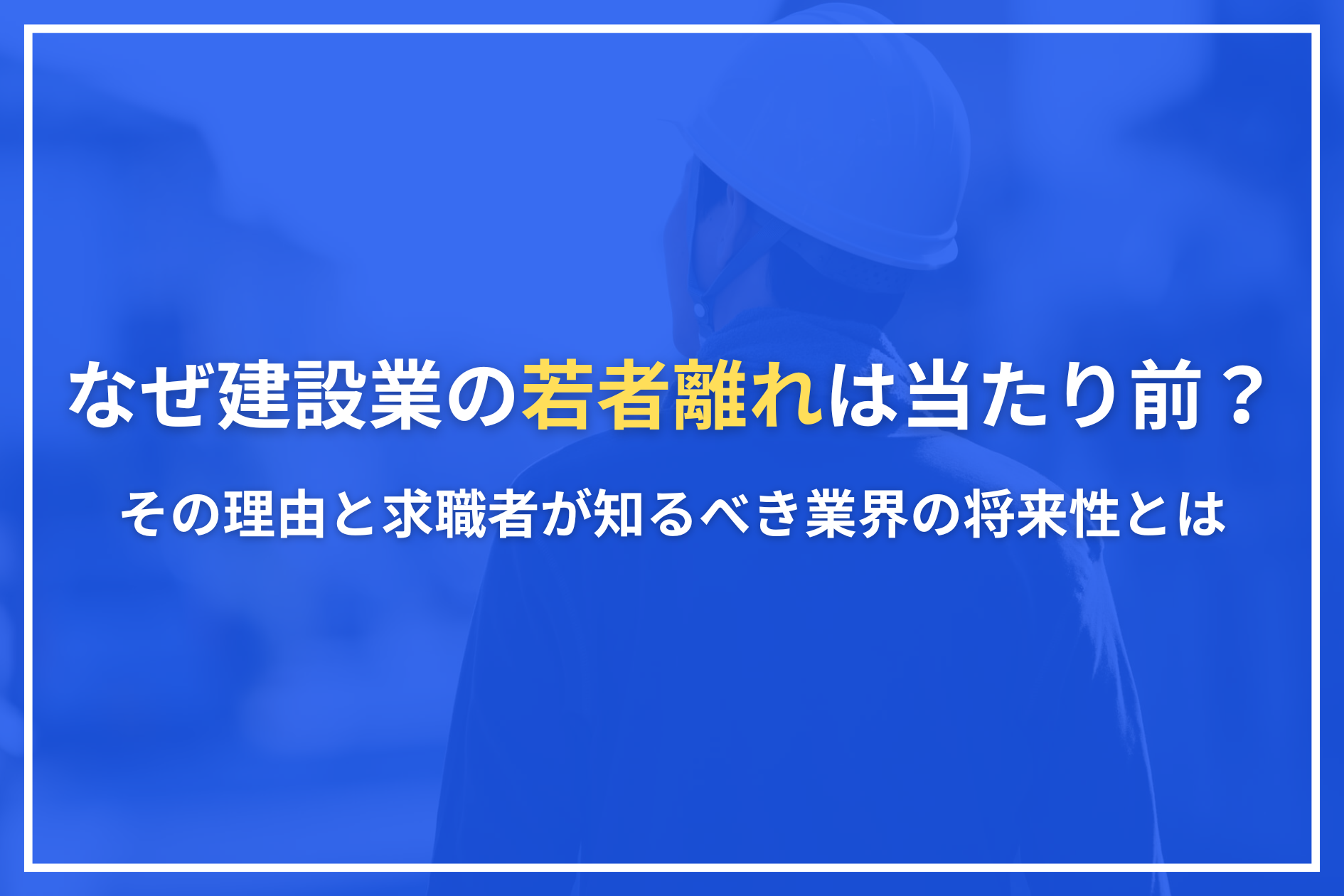
「建設業はきつそう…」「若い人がどんどん辞めているイメージがある…」
もしかしたら、あなたもそんなイメージを持っているかもしれません。たしかに、長時間労働や「3K」といった印象から、建設業界の若者離れは深刻な課題とされてきました。
しかし、その「当たり前」は今、大きな転換期を迎えています。
この記事では、なぜ建設業の若者離れが「当たり前」と言われてきたのか、その理由をデータとともにお伝えします。そして、その先にある、未経験の求職者だからこそ知ってほしい業界の大きな「可能性」について、徹底的に解説します。
建設業界の若者離れは本当なの?【データで見る現状】

建設業界で若者が少ないとよく言われますが、実際のところはどうなのでしょう。まずは国や省庁が示す統計データをもとに、人材の年齢構成や離職率、求人状況を整理してみます。
年齢構成
国土交通省の調査によると、建設業の就業者のうち55歳以上は約35%を占めています。一方で、29歳以下はわずか12%にとどまります。全産業平均では16%前後が29歳以下であることを考えると、建設業の若年層比率が低いことは明らかです。高齢化が進み、世代交代が難しい状況にあることがわかります。
(出典:国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」2024年)
離職率
厚生労働省のデータでは、高校卒業後に建設業へ就職した人の3年以内離職率は4割を超えています。これは全産業の平均よりも高い水準であり、「若者が入職しても辞めてしまう」というイメージが、残念ながらデータによって裏付けられているのが現状です。
有効求人倍率
人手不足の深刻さは求人倍率からも明らかです。厚生労働省の令和7年7月の調査によれば、全業種の有効求人倍率(パート含む)が1.09倍であるのに対し、建設業は5.04倍と非常に高い水準です。さらに内訳を見ると、「建設躯体工事従事者」は7.65倍、「土木作業従事者」は6.21倍に達しています。これは「一人の求職者に対して6社以上が求人を出している」という状況を意味します。
企業側は深刻な人手不足に悩んでいますが、見方を変えれば、これは求職者にとって大きなチャンスがあることを示しており、「若くて意欲のある人材」が強く求められているのです。
(出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年7月分)」2025年)
建設業の若者離れは「当たり前」と言われる理由

建設業は長時間労働や3Kのイメージなど、若者が避ける理由がいくつも指摘されてきました。ここでは、長らく「当たり前」と見なされてきた環境や慣習を整理し、なぜ若年層が定着しにくいのか、理由を見てみましょう。
労働環境の問題
建設業は他の産業に比べて労働時間が長く、休日が少ない傾向があります。年間総実労働時間は全産業平均が1636時間であるのに対し、建設業は1972時間と1.2倍近く長くなっています。また、週休二日制の導入率も全産業が53.3%であるのに対し、建設業は令和5年の調査では40.7%にとどまり、休みが取りにくい環境が若者に敬遠される理由になっています。
「3K」に代表されるネガティブな業界イメージ
「きつい・汚い・危険」という「3K」のイメージは依然として根強く残っています。加えて、「上下関係が厳しいのでは」「パワハラが多そう」といったマイナスの印象も若手の目には強く映り、建設業界への就職をためらう要因になっています。
古い慣習や考え方
建設業界には年功序列やアナログな働き方が根強く残っています。たとえば、いまだに電話やFAXが中心で、メールやチャットツールが十分に活用されていない職場もあります。こうしたデジタル化の遅れは効率を下げるだけでなく、若い世代にとって魅力を感じにくい環境をつくっています。
給与・待遇への不満
仕事の厳しさや拘束時間に見合った給与が得られない、という不満も大きな理由です。特に、天候によって仕事がなくなり、収入が不安定になりがちな「日給月給制」などの雇用形態は、安定した生活を望む若者にとって大きな不安材料となっていました。
その「当たり前」はもう古い!建設業界が推進する若者離れ対策とは?

一方で、かつて常識とされた環境や慣習は今、大きく変わり始めています。労働環境の改善やデジタル化、教育制度の整備といった動きにより、若い人が「やってみたい」と思える環境に近づきつつあります。
「新3K(給与・休暇・希望)」へ!国も後押しする待遇改善
2024年4月から建設業にも罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されました。これにより、かつてのような長時間労働は法律で制限され、業界にとって大きな転換点となっています。さらに夏場の酷暑対策としては、国が「熱中症予防指針」を示し、危険な環境下での連続作業を制限するなど、法律やガイドラインに基づいた安全確保も強化されています。
また、仕事内容やスキルに見合った給与体系への見直しや、週休二日制の導入も進んでおり、本格的に待遇面の改善に取り組む企業が増えています。国や業界団体も後押しし、『給与・休暇・希望』という新しい「3K」を重視する動きが広がっています。
IT化で「きつい」を軽減!DXが現場の常識に
建設現場ではICTやBIM/CIM※といったデジタル技術の活用が進み、作業の効率化や安全性の向上につながっています。たとえば、ドローンによる測量や3Dモデルを用いた施工管理により、肉体的な負担や危険な作業を減らすことが業界のスタンダードになりつつあります。このようにデジタル技術のおかげで、「きつい・危険」と言われてきた作業の負担が減ってきています。
※BIM(Building Information Modeling)、CIM(Construction Information Modeling):建物や土木構造物を3次元モデルで一元管理し、設計から施工・維持管理までを効率化する技術。
未経験者が育ちやすい環境へのシフト
従来は「見て覚えろ」という育成方法でしたが、未経験者でも効率よく仕事を覚えやすいよう、体系的な研修やマニュアル整備が一般的になりつつあります。メンター制度の導入や資格取得の支援など、未経験者が安心して成長できる環境づくりが定着してきました。人手不足の中で若手を育てることは、企業の存続に直結する重要な取り組みとなっています。
未経験者も大歓迎!人手不足の今こそ、建設業がおすすめな理由

ここまで読んで、建設業界のイメージが少し変わってきたのではないでしょうか。最後に、なぜ「今、未経験者にこそ」建設業をおすすめしたいのか、その理由をお伝えします。
理由1:一生もののスキルを身につけられる。AIに奪われない専門職
建設業は人々の生活を支えるインフラを担う仕事です。建設投資額も増加傾向にあり、防災や国土強靱化の政策からも需要が続いています。現場で習得した技術や資格は全国で通用し、一度身につければ長く活かせます。AIやロボットは作業を補助する存在にとどまり、最終的な判断や技術は人間にしか担えません。
さらに、資格を取得することで安定した収入を確保しやすくなります。たとえば「一級・二級建築施工管理技士」や「土木施工管理技士」といった国家資格は、現場での責任ある立場を担ううえで必須とされ、給与や待遇の向上に直結します。資格手当や昇進につながるケースも多く、「稼げる専門職」としての強みを持てるでしょう。
理由2:ライバルが少ない今こそチャンス。ゼロからでも評価される世界
若者が少ない業界だからこそ、やる気のある人材はとても重宝されます。学歴や経歴にとらわれず、意欲次第で早い段階から責任ある仕事を任されることもあります。ゼロからの挑戦であっても、努力や姿勢がしっかり評価されやすいのは、いまの建設業ならではの特徴です。
理由3:地図に残る仕事。仲間と創り上げる達成感と社会貢献
自分たちが汗を流して創り上げたものが、橋やビルとして何十年も地図に残り、人々の生活を支える。これほど大きな達成感と社会に貢献している実感を得られる仕事は、他にそう多くはありません。困難な仕事をチーム全員で乗り越え、完成した時の喜びは、何物にも代えがたい経験となるはずです。
》建設業の平均年収って実際どう?国の最新統計で業界別・職種別に徹底比較!
》現場仕事の種類って何がある?現場のリアルなやりがいや未経験からの始め方を紹介
まとめ

建設業は長時間労働や3Kのイメージなどから「若者離れが当たり前」と言われてきました。しかし今では、労働環境の改善、デジタル技術の導入、未経験者育成の仕組みが定着し、古い常識や仕事内容、働く環境が変わりつつあります。
人手不足の今だからこそ、未経験から挑戦できるチャンスが大きく開かれています。一度技術を身につければ長く活かすことができ、しっかり稼ぎながら安定した働き方やキャリアアップにもつながります。
これまでのイメージにとらわれず、新しい建設業界の姿を知り、少しでも「やってみたい」と感じたら、ぜひ一歩を踏み出してみてください。新しい建設業界で、自分の力を活かしてみませんか?
新しい建設業界へ。その第一歩を「キャリコンジョブ」で踏み出そう。
ここまでお読みいただき、建設業界のイメージが大きく変わったのではないでしょうか。かつての「3K」から「新3K」へ、そしてテクノロジーと新しい教育体制が当たり前になる未来へ、業界は確実に歩みを進めています。
しかし、最も重要なのは、こうした変化を本気で推進している「成長できる企業」と出会うことです。
建設業界に特化した求人サイト「キャリコンジョブ」は、そのための最適な場所です。私たちは、未経験者を大切に育てる研修制度が充実した会社や、週休2日制といった待遇改善に本気で取り組む会社、そしてあなたの未来のキャリアを一緒に考えてくれるような、この記事でご紹介した「新しい働き方」を実践する優良企業の求人を多数掲載しています。
業界の未来を創る一員として、あなたにふさわしいキャリアを見つけるお手伝いをさせてください。


.png)

.png)